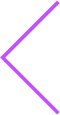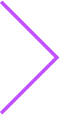NEWS&topics
COLUMN 2024/10/08岐阜の窯元で生まれる特別な一杯:hugcoffeeオリジナルマグの誕生ストーリー

岐阜県多治見市にある「丸朝製陶所」は、100年以上の歴史を持つ窯元🎨。
hugcoffeeのオリジナルマグも、ここで一つひとつ丁寧に作られています☕️。
先日、この丸朝製陶所を訪れて、マグがどんなふうに作られているのかを見学させていただきました👀。
9月中旬でしたが、まだまだ岐阜県は暑かった〜。
工場に足を踏み入れると、製造中のカップや、成形型、釉薬がたくさん並び、まるで博物館のようでした✨。
天井にはゆっくり動く小さなゴンドラが見え、
巨大な機械や窯がまるで生き物のように動いていました。
その光景は、まるで工場全体が一つの大きなアトラクションのようで🎡
作り手を担う従業員さんの情熱を間近で感じられました🔥。
工場内のゴンドラは1周回るのに2時間以上かかるのだとか😳
⇧工場内のコンベアの様子
hugcoffeeのオリジナルマグをはじめ
まず「土練り」から始まります。工場の片隅に置かれたさまざまな種類の素地。
良質の粘土鉱物を大量に含む豊かな土壌を有するのが岐阜県で作られ続けている理由の一つ。
⇧素地と呼ばれる陶磁器の素材になる土
そして、「自動成形機」と呼ばれる機械で人がロクロを回すような技術を使ってマグの形が作られていきます。
機械で主なマグの形が成形されますが、
マグカップに欠かせない持ち手は、一つ一つ職人さんの手で取り付けられています。
その丁寧な手作業がマグに温かみを与えてくれる👐
そんな気がします。
⇧「自動成形機」の様子

⇧ひとつひとつ持ち手を付けていく
成形が終わると、カップを乾燥し「素焼き」という工程🌬。
11時間から12時間、トンネルのような窯で焼かれます。
ここで少し強度が増し、その後に釉薬をかける準備を整えます✨
釉薬をカップに浸すことで、あの美しい光沢が生まれるんですよ💫。
⇧素焼きされていくトンネル状の窯

⇧釉薬に通す
釉薬に通した時点では、マグが何色に仕上がるのか、正直わかりません。
焼いた時の化学反応で色が着くそう👀
「焼き物を科学する」という言葉があっている気がします。
窯での焼き方、温度によっても色が変わってくるそうで、
まさに芸術作品そのものなのだと。
転写式のものはここでシルクスクリーンを行い、
そして「本焼成」🔥
⇧シルクスクリーンする機械
窯の中で1300℃という高温で
24時間かけ、空気の量なども調整し、
「焼き”締める”」
hugcoffeeの今回のマグはこの後に
スクリーンを貼って、乾燥させて
もう一度4時間程度焼いて完成するそう。
⇧窯に入れる前の陶磁器たち

⇧4800個を一気に焼ける大きさ
長い長い工程を経て、マグが作られているのです。
初めて、訪れた丸朝製陶所。
実際にお邪魔してみることで、
私たちがみなさんの元にお届けしているオリジナルマグが
もっと魅力的で、もっとストーリーを秘めたものに。
製造工程や作家の思いを知ってもらうことと、
器が日常生活に溶け込むことでもっと器が好きになる
日々のコーヒータイムをさらに豊かにしてくれるはずです。

この特別なマグが、もうすぐあなたの手元にも届きます📦。
どうぞ楽しみにしていてくださいね😊。